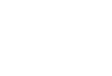モノが余りだすと、モノが提供する単純な機能はあたりまえであり、その機能がその個人の価値観をどう満足させるかが焦点となってきた。こうしたニーズにどう応えるか、それがコラボレーションの力だ。
かつてレビットは、「人は化粧品ではなく化粧品が約束する魅力を、直径1/4インチのドリルではなく、その大きさの穴を消費するのだ」と語った。顧客はその商品そのものを買うのではなく、その商品が与えるベネフィットを買うという意味であり、マーケティングに携わる人なら誰でも知っている言葉だ。
モノへの欲求が強かった時代では、より高機能でより低コストという単純な提供側の論理があればモノは売れた。その商品の持つ機能や新たな技術が、シンプルなベネフィットを訴求すればよかった。
ドリルの持つ機能は単純にドリルが空ける穴であり、機能・利便性であり、その穴をどう使うか、その穴で何が実現するのかのバリエーションを提案するまでもなかった。市場には「穴」そのものが不足していたからだ。顧客はその穴を空けるモノを探していたのだ。その他にも、簡単で便利な調理器具、食事、そのもの自体が不足しており、モノが提供する単純な費用対効果を考えれば十分だった。
モノ余り時代のベネフィット
しかし、やがてモノが余りだすと、そうしたモノが提供する単純な機能はあたりまえであり、その機能がその個人の価値観をどう満足させるかが焦点となってきた。機能の単純比較では、具体的な使用価値を見出すのは難しく、「100メガのメモリーに3ギガのハードディスクと150メガのメモリーに2ギガのハードディスク」と言われても、それが何を表しているのかを考えることは、経験を持たない顧客ではできないからだ。
提供する側の想像する価値とは異なる価値を顧客側が見出し、思わぬ大ヒット商品が生まれるのもこうした背景があった。子供用に売り出したものが大人に爆発的に売れたり、その逆でヒットしたり、そうした例は枚挙にいとまがない。
このように、売り手が意識してもしなくても、顧客自らがその後のベネフィットを考え、認め購入するに至ることも多いのだが、作り手側として、それを市場の偶然に任せるわけにはいかない。しかし、その分顧客が持つ一歩進んだ価値をつく手側があらかじめ作り上げるのは簡単ではない。なにせ、誰も想像できていないのだから。
また、作り手の認識が甘すぎてしまうと、購入後には与えられると勘違いしていた価値が、顧客側から評価されないとなると、元々得られると思っていた価値とのギャップを生んでしまい、ブランド価値が失墜ししまうことも少なくない。
自分たちの商品だけで顧客のベネフィットをより高度に満足させ続けていくのは至難の業だ。商品提供側からの視点を変えろと言われても、簡単にできることではない。
次のページコラボレーションの力
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2015.07.10
2015.07.24