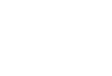フレックスタイム制度が組織運営に与えた影響を振り返っておくことは、管理職の能力向上を考える上で大変重要なことです。
20年と少し前、新卒で入ったリクルートグループの会社では、全ての部署ではありませんでしたが、朝9時の始業前、8時50分から全員が集まって軽く体操をしていたことを思い出します。体操が終わると朝の掛け声というのがあり、皆で「頑張るぞ。オーっ!」などと言ってから仕事に取り掛かっていました。
フレックスタイムなどという言葉も概念も知らず、朝に全員が揃うのは当たり前のことで、日本全体の年間の平均総労働時間が2,200時間くらいの頃です。それからしばらくして、「日本人は働きすぎだ。」「余暇を増やすことは心身の健康にいいし、旅行などの内需を増やすから経済成長にもつながる。」といった議論が国主導で始まり、1,800時間が目標として設定されました。
以降、徐々に労働時間が減っていき、現在ではその数値がほぼ達成されているわけですが、企業がやったことは残業を(表面的に・・という部分もありますが)減らすことと、働き方の自由度を上げることで、これらの中心的な役割を果たしたのがフレックスタイム制度の普及でありました。
毎日9時から退社までの時間が労働時間ということではなく、出社・退社の時間に自由度を持たせて、労働時間は月単位でまとめて本人から申請させるといった仕組みで、実態は別にして、1,800時間の達成には最も大きな役割を果たしたと言えるでしょう。それは良かったとして、一方でフレックスタイム制度の陰の部分も考えておく必要があります。
よく覚えていますが、フレックスタイムの導入時、現場の管理職から「朝会が出来なくなる」「規律が緩むのではないか」といった声が多く上がりました。朝、バラバラにやって来るような仕組みに違和感を抱く現場の声に対して、人事部には「各々の業務の状況に合わせて働くことが合理的であり、心身の健康にもつながり、業務にもかえって良い効果が期待できる。」といった大義名分があり、朝会などは小さな話に感じて「そこは工夫をしてやってください」などと返答していた訳ですが、振り返ってみれば、現場が危惧した部分が現実になったのではないかと感じます。
つまり、フレックスタイムの自由さが組織の緩みにつながった面は否定できないのではないか、労働時間が減って心身が健康になったかと言えばそうでもないし、出来た余暇が有効利用されイノベーションにつながったかと言うとそうでもない。結局、超過勤務手当の削減が達成されただけではなかったか。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13
NPO法人・老いの工学研究所 理事長
高齢期の心身の健康や幸福感に関する研究者。暮らす環境や生活スタイルに焦点を当て、単なる体の健康だけでなく、暮らし全体、人生全体という広い視野から、ポジティブになれるたくさんのエビデンスとともに、高齢者にエールを送る講演を行っています。
 フォローして川口 雅裕の新着記事を受け取る
フォローして川口 雅裕の新着記事を受け取る