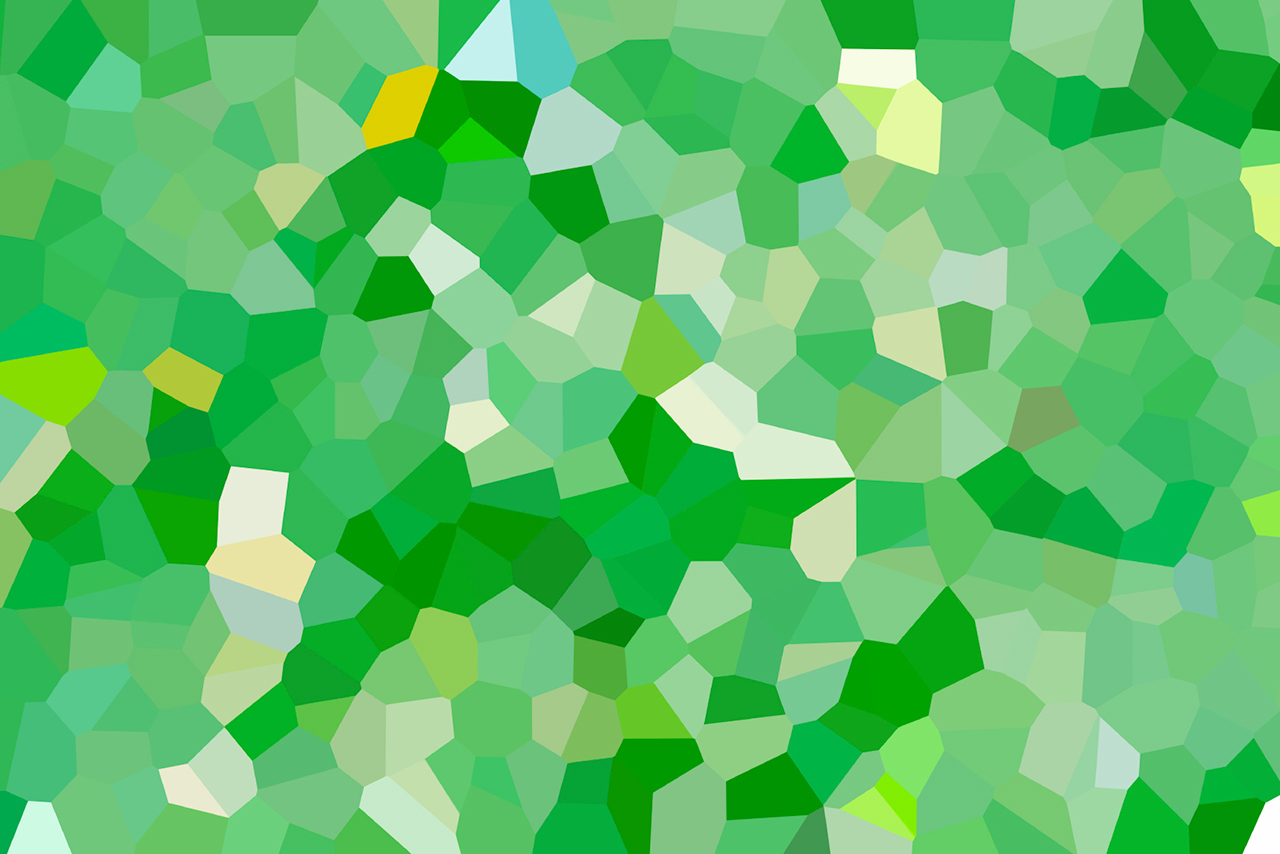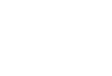コンピュータソフトといえば、自社専用に開発するもの。そんな認識が主流だった日本に、本格的なパッケージソフトを持ち込み、普及を促したのがビル・トッテン社長率いるアシスト社だ。同社成長の歩みは、日本のパッケージソフト市場成長の歩みでもある。

第2回「アシスト社、創業の産みの苦しみ」

■競合がいて初めて市場は立ち上がる
「永妻さんはよりによって『MARK IV』を、僕たちの競合となる相手に紹介したんです」
そもそも日本とアメリカのソフトウェア市場には、大きな不均衡があった。情報不足のために日本企業は、パッケージソフトのメリットをまったく理解していなかったのだ。ソフトといえば、自社の業務内容に合わせて自分たちで作るもの。これが当時の日本の常識である。
「情報の不均衡あるところ、必ずチャンスあり。これはビジネスの鉄則ですね。だから僕はアメリカの会社を辞めてまで日本に乗り込んできたのです。扱う商品も決まり、さあこれから売りまくるぞというときに、わざわざ競合を作ろうとする。永妻さんの考えていることが、最初はまったく理解できませんでした」
ところが、この永妻氏の行動こそが、日本にパッケージソフト市場を立ち上げる上では決定的に重要だったのだ。その真意を理解するためには、仮に日本市場にトッテン氏の扱う『ASI-ST』しか存在しなかったらどうなったかを少し考えてみればよい。
「日本ではまだ誰もパッケージソフトの良さを知りません。しかも、そのソフトを広めようとしているのは外人、つまり僕のことです。こいつは商売がうまくいかないとなれば、いつアメリカに逃げ帰るかもしれない。そんな奴だけが扱っている製品、それもこれまでの日本では誰も知らなかった製品の話を、誰が真剣に聞いてくれるでしょうか」
では、競合他社、それも日本企業が、時を同じくして同じジャンルの製品を扱い始めたらどうなるだろうか。競合二社は当然お互いに切磋琢磨し合い、マーケットでの認知度を高めるべく啓蒙活動に励むだろう。トッテン氏はアメリカ人だが、競合社は純然とした日本企業である。日本人が誠意を込めて話をすれば、日本企業もむげに拒否はしないだろう。
「結局、競合する二社が競い合うことはお互いによい刺激になるし、何よりマーケット全体が活性化するわけです。この相乗効果を永妻さんは読んでいたのでしょう」
だからといってすぐに売れたというほど甘い話ではない。何しろ、日本では初めてのパッケージソフトである。どの会社も使ったことがないソフトを導入するのには、相当な勇気が求められる。トッテン氏を招いたシステム開発株式会社内でも、パッケージソフト販売に対する不協和音が響き始めていた。
■分離、独立、そして初めての顧客獲得へ
次のページ『株式会社アシスト 関連リンク』
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
FMO第34弾【株式会社アシスト】
2010.05.20
2010.05.13
2010.05.06
2010.04.30